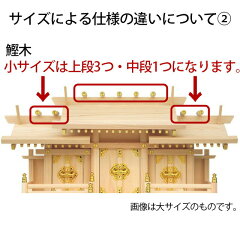ポイント
来年2023年『令和5年』は60年に一度の癸卯(みずのとう)です。
長い日本の歴史を経て生まれた年中行事は生活の中で培われた知恵の結晶といえます。日本人が昔から守り、伝え続けてきた『しきたり』。それはなぜ、どうやって生まれたのでしょうか?しきたりは途絶えさせたくない『日本人の心』です。しきたりを意識して生活してみてはいかがでしょうか?

しきたりとは?
正月のならわし、年越しの準備
門松
〇正月事始めから始める歳神様を迎える準備
皆さんは門松を飾りますか?門松は歳神様が降りてくるための目印なんです。
新しい年を迎えるための準備は12月13日から始め、28日までに終わらせると
されてます。
13日は『正月事始め』と呼ばれ、歳神様を迎える準備をします。
歳神様とは大自然の根源的な生命力とも考えられ、新しい年の
命を授けてくれる神様です。
そんな歳神様を迎えるために掃除を始める日でもあります。
13日には、もう一つ古くからの習慣の『松迎え』が行われてい
ました。
これは門松などの正月飾りに使う松を山へ取りに行くことです。
また、歳神様を山から迎えることを意味するという地域もありま
す。
鏡餅や、門松など正月飾りを飾るのは、12月28日までがよいとさ
れています。
これは29日は『二重苦』と読め、31日は『一夜飾り』という礼を
逸した行為と考えられていたからです。
〇門松の竹の意味
竹は曲がることなく、節がまっすぐ伸びることから、早い成長を象徴するおめでたいものとされ、門松に添えられるようになりました。
〇梅の意味
気品のある芳香が好まれる梅は、古来より縁起のよい物とされた。門松の土台を結ぶ際には、梅の花の形を模した梅結びが用いられる。
〇松の意味
松は一年中青々として葉を落とさない常緑樹であり、生命力の象徴。また、神様が宿る木と伝えられ、神様を『待つ』という意味もあります。
しめ飾り
〇しめ飾りを起源にして豪華な作りになっていった
しめ飾りも門松と同様、歳神様を迎えるためのもので、その由来は『古事記』にまでさかのぼる。
天の岩屋戸(あまのいわやど)に閉じこもっていた天照大神が、再び隠れることのないように、岩戸の入り口にしめ縄を渡したのが起源とされている。
これは神聖な場所と外界を分ける役割を持つとされている。
〇橙(だいだい)
実が熟しても枝から落ちにくいため、縁起がよいとされる。家が「代々」栄えるという意味を込めて飾る。他の柑橘類での代用も可。
〇扇
扇の形は末広がりで縁起がよいとされる。子孫繁栄や商売繁盛を願って、正月飾りだけでなく、お祝いの席でも用いられる。
〇稲穂
稲穂は豊作の印。収穫への感謝と五穀豊穣への願いを込めて飾る。その土地の特産物を飾ってもよい。
〇紙垂(しで)
紙を四角に切って垂らしたもので、稲の穂が垂れた形を模しているとされる。その内側が清浄であることを示す役割を持っている。
〇杉葉
寿命が長く神聖な木である杉は、縁起がよいとされる。ほかには、裏白(うらじろ)やゆずり葉、ほんだわらなども飾られる。
歳神棚
ポイント
-

-
洗って落とせる1Dayヘアカラーチェンジ『エマジニー』って知ってる?
1日だけまたは数時間だけ髪色を変えたいと 思ったことありませんか?エマジニーならそ れは可能です。 使い方 落し方 成分 〇1日だけイメチェンをしたい! 〇自分だけの髪色を作りたい! 〇地毛にダメージ ...
続きを見る